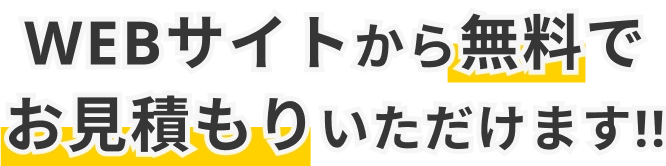こんにちは!仙台解体センターです。
近年、「親から空き家を相続したけれど、使う予定がない」「老朽化していて管理が大変」「相続放棄をしたいけれどどうすればいいのかわからない」といった相談が増えています。
空き家の相続放棄は単に「権利を手放す」だけでなく、法律・税金・管理・解体など多くの要素が絡み合う複雑な手続きです。
この記事では、「空き家 相続 放棄」というテーマで、放棄の基本から注意点、放置した場合のリスク、解体や補助金の情報までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、「放棄した後に責任が残るケース」「解体のタイミング」「行政支援を受ける方法」などが具体的に分かります。
「相続放棄したつもりなのに固定資産税の請求が届いた」「老朽化した空き家が倒壊しそうで不安」と感じている方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
相続放棄とは?空き家の所有権が残るケースに注意
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスの財産とマイナスの財産)をすべて引き継がない手続きです。家庭裁判所に申述して受理されると、最初から相続人でなかったことになります。
しかし注意したいのは、放棄をしても「所有者」とみなされる期間が一時的に存在することです。
登記情報が更新されるまでの間は、税金や管理責任の請求が自分に届くことがあり、実際に「固定資産税の納税通知が届いた」という相談も少なくありません。
また、相続放棄をしても、放棄の手続き中に建物が損壊し第三者に被害を与えた場合、「占有者」として責任を問われることがあります。
そのため、放棄を検討する際は、手続きの時期や空き家の現状を把握し、放棄完了までのリスク管理を行うことが重要です。
相続放棄しても管理義務が残る?知っておきたい法律のポイント
2021年の民法改正により、相続放棄をしても次の相続人が決まるまで空き家を管理する義務が明確化されました。
つまり、「放棄したから放っておいていい」というわけではなく、建物の倒壊・崩落・不法侵入などを防ぐための最低限の管理が必要になります。
たとえば、屋根瓦が落下しそうな状態や、外壁の一部が崩れかけている状態を放置していると、近隣住民から通報され、自治体から勧告や指導を受ける可能性があります。
さらに、特定空家等に指定されると、固定資産税の軽減が外れ、税額が最大6倍になるケースもあります。
管理義務は法律で定められており、怠ると行政代執行や損害賠償に発展することもあるため、放棄手続きと同時に管理方法を決めておくことが大切です。
司法書士や弁護士だけでなく、空き家管理を請け負う専門業者や解体会社に相談して、現状のリスクを最小限に抑えましょう。
空き家を放置するとどうなる?行政代執行や費用負担のリスク
空き家を長期間放置してしまうと、次のようなリスクが発生します。
- 行政代執行のリスク
老朽化や倒壊の危険があると自治体から勧告が出され、改善されない場合は強制的に解体(代執行)されます。
その際の費用は数百万円規模になり、後から請求されることもあります。 - 固定資産税の増加
空き家のまま放置して特定空家に指定されると、「住宅用地特例」が適用されなくなり、税額が最大6倍に増えることがあります。 - 防犯・衛生・景観の悪化
空き家は不法侵入や放火、不法投棄の温床になりやすく、近隣とのトラブルの原因になります。
実際に全国で年間約3,000件以上の火災が空き家で発生しているといわれています。 - 資産価値の低下
放置された空き家は建物自体の価値が急速に下がるだけでなく、土地の評価額も下がる傾向があります。いざ売ろうとしても買い手がつかない状況に陥ります。
このようなリスクを回避するためには、「放棄する前にどう処分するか」を早い段階で考えることが重要です。
相続放棄前に検討すべき3つの選択肢|売却・寄付・解体
相続放棄を考える前に、次の3つの選択肢を検討しましょう。
1. 売却
不動産会社に依頼して空き家を売却する方法です。
老朽化していても、立地が良ければ「更地にすれば売れる」ケースがあります。
建物付きだと買い手が見つからなくても、解体して更地にすることで再利用価値が高まり、売却成立率が上がります。
2. 寄付
空き家を自治体やNPOに寄付する方法もありますが、現実的には受け入れ先が限られています。
自治体は管理コストがかかるため、建物の状態が悪いと断られることが多いです。
しかし、歴史的建造物や地域活性化の拠点として使える場合は、寄付が受け入れられる例もあります。
3. 解体
もっとも確実な方法が空き家の解体です。
解体することで、倒壊や火災のリスクを防ぎ、土地の価値を保つことができます。
また、更地にした後は駐車場や貸地などに活用することで、固定費を収益に変えることも可能です。
特に老朽化が進んだ建物では、修繕よりも解体の方が長期的に見て経済的な選択となる場合が多いです。
トラブルを防ぐための実践的ステップ|専門業者・司法書士への相談のすすめ
空き家の相続放棄を検討する場合は、以下のステップを踏むことでトラブルを防げます。
- 司法書士・弁護士に相談する
相続放棄の申述には期限があります。被相続人が亡くなってから3か月以内が原則です。
専門家に相談すれば、資産状況の確認から申述書の作成、提出までスムーズに進められます。 - 現地調査を行う
空き家の劣化状況を把握するために、専門業者による現地調査を行いましょう。
建物の傾き、基礎の劣化、屋根や外壁の崩れなどを確認することで、放置リスクを明確にできます。 - 解体費用の見積もりを取る
老朽化が激しい場合は、複数の解体業者に見積もりを依頼します。
木造住宅30坪の場合、平均費用は100〜150万円前後が目安です。
見積もりの内訳(重機費、廃材処分費、人件費)を確認し、後から追加費用が発生しないようにしましょう。 - 補助金制度を確認する
自治体によっては、空き家解体費用の一部を補助する制度があります。
補助金は上限30〜100万円程度が多く、申請前に見積書や写真の提出が必要です。
放棄前に解体を検討する場合は、補助金の申請タイミングが非常に重要になります。 - 放棄後の管理を委託する
放棄手続き中や完了までの間も、管理義務は続きます。
専門業者に清掃・草刈り・巡回点検を依頼することで、トラブルを防止できます。
空き家解体の補助金と行政支援制度
全国の自治体では、老朽化した空き家の増加に対応するため、解体や除却に関する補助制度を整備しています。
たとえば、以下のような支援内容が一般的です。
- 補助金の上限額:30〜100万円程度
- 対象条件:危険な状態の空き家、または長期間放置されている住宅
- 必要書類:所有者確認書類、現地写真、見積書、登記事項証明書など
補助金は「工事前の申請」が原則で、着工後に申請しても受けられないことがあります。
また、自治体によっては解体後の土地活用に関する相談窓口を設けているところもあり、駐車場化や売却サポートなどを受けられる場合もあります。
相続放棄を検討している場合でも、手続き前に一度解体・補助金の検討を行うことで、トラブルを防げることがあります。
専門業者に相談すれば、補助金の条件確認から書類の作成までサポートしてもらえます。
まとめ
空き家の相続放棄は、一見「手放せば終わり」と思われがちですが、実際には管理・税金・解体・補助金といった複数の問題が関係しています。
放棄した後に責任や費用が発生するケースもあるため、安易な判断は禁物です。
空き家を放棄する前に、「売却・寄付・解体」の選択肢を比較し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
とくに解体を選ぶ場合は、補助金や自治体支援制度を活用することで、費用負担を大きく軽減できます。
仙台解体センターでは、地域密着をモットーに空き家、建て替え時の解体作業をおこなっております。
是非!解体の事なら仙台解体センターにお任せください!